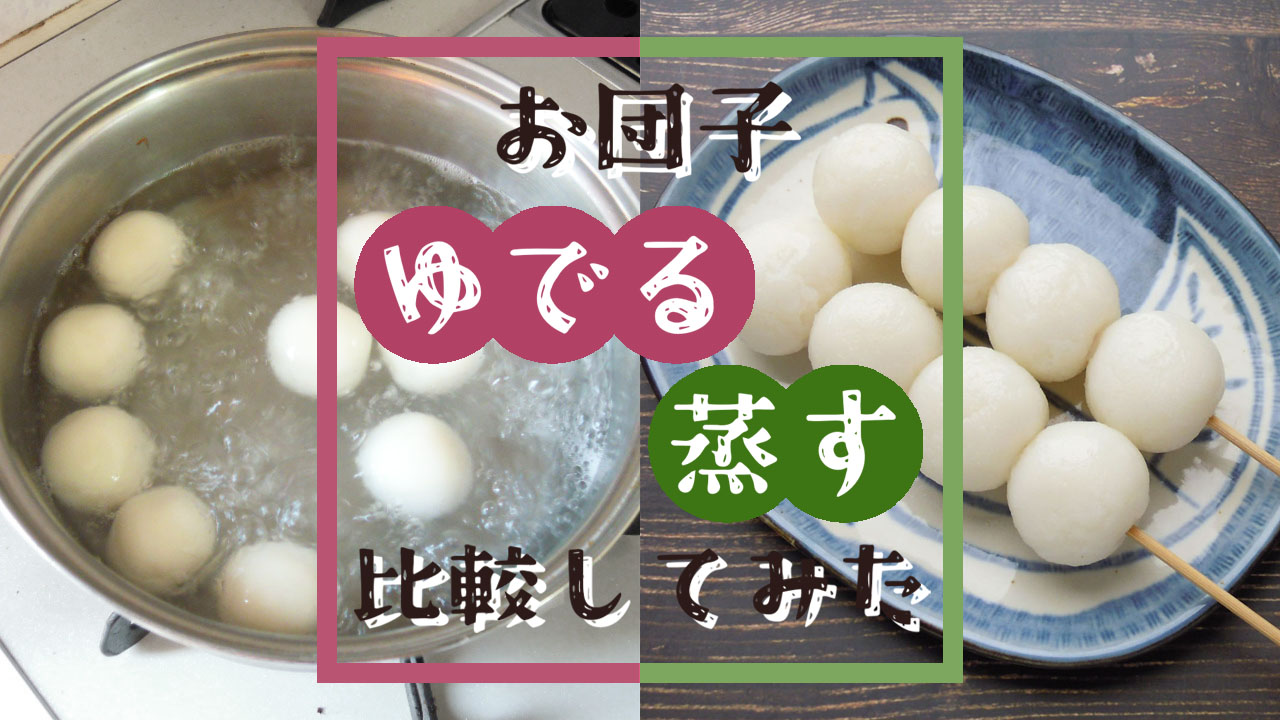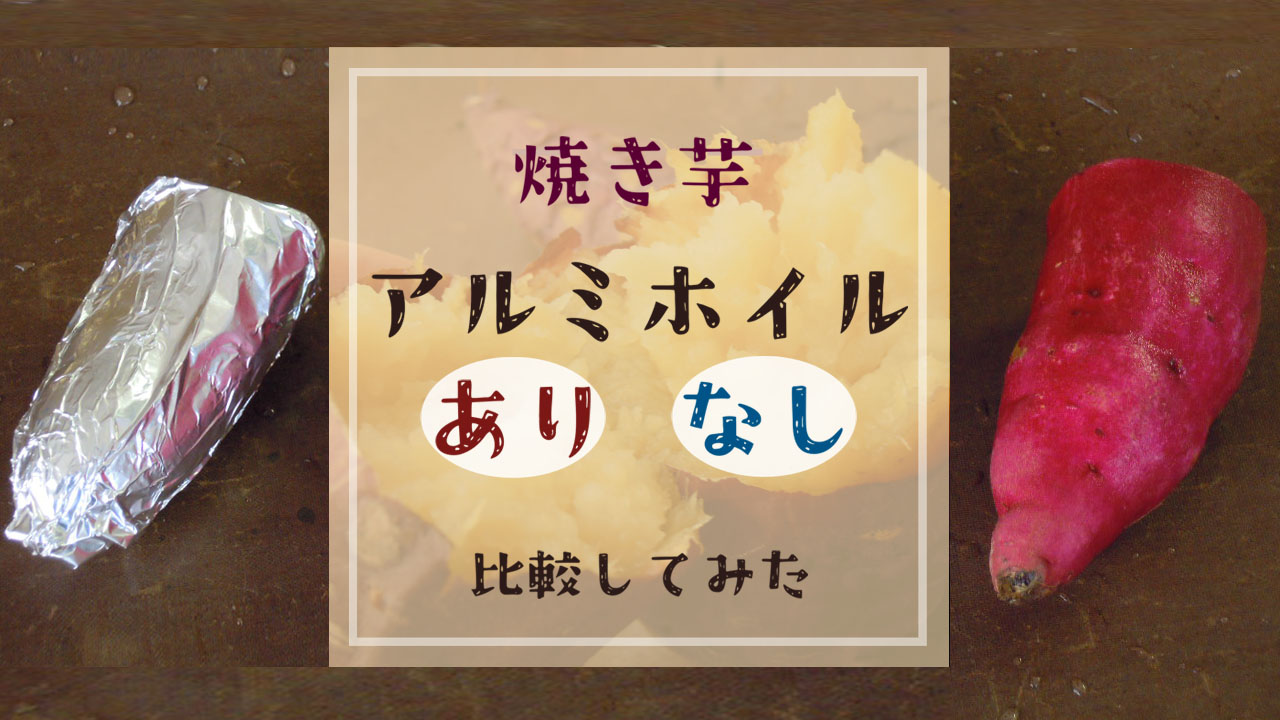渋切りありとなし、2つのあんこを食べ比べてみた
小豆をゆでる際、ゆで汁をすべて捨ててアクを取り除く「渋切り」という工程があります。
この渋切り、絶対に必要なのでしょうか?
ていねいにアクを取り除けばクセがなく食べやすいあんこが出来上がりそうですが、それと同時に小豆のうまみや風味が失われている可能性はないのでしょうか。
自分はもともと小豆の風味が強いあんこが好みだったので、渋切りをしないあんこの方が好きかもしれないと思い、実際に二つのあんこを作って食べ比べてみました。
関連記事
実験の概要
今回の実験では、以下の条件で作ったつぶあんを食べ比べます(細字はAB共通の条件)。
【 A 渋切りあり 】
- つぶあん
- 小豆10:きび砂糖9
- 渋切り1回
【 B 渋切りなし 】
- つぶあん
- 小豆10:きび砂糖9
- 渋切りを一切しない
- ゆで汁も捨てずに使う
以下、A.渋切りありのあんこを「あり」、B.渋切りなしのあんこを「なし」と省略します。
「なし」は小豆のゆで汁も捨てずに利用し、小豆の味を一切に逃さないように仕上げます。
砂糖はヴィーガン※対応のあんこにするために、白砂糖ではなくきび砂糖を使用します。
あんこ に使う砂糖は「グラニュー糖」や「白ざら糖」と言った雑味のないものが良いとされていますが、きび砂糖を使うとどうなるのかも渋切りの有無と同時に検証していきたいと思います。
ヴィーガンとは
動物由来の食品や製品を食べない・使用しない人のこと。白砂糖の精製には動物の骨が使われている。
使用した食材

小豆はこちらを使用しました。
新豆ではなく、収穫から時間のたったものを使用しました。
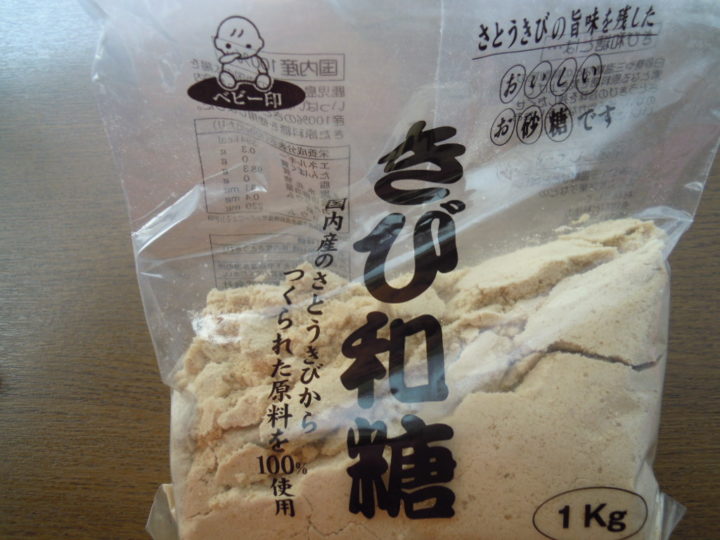
砂糖はこちらを使用しました。
正確には「きび和糖」という商品名なのですが、わかりやすいように以下「きび砂糖」と表記します。
あんこの作り方
あんこの詳しい作り方は以下の通りです。
「なし」では2番目の工程「渋切り」は省略し、4番目の工程の「水少量」には小豆のゆで汁を使用します。
材料
小豆(乾燥) …… 187.5g
きび砂糖 …… 169g
作り方
- 小豆を戻す
- 乾燥小豆を洗って熱湯に浸し、一晩置く。
- 渋切り
- 小豆を戻し汁ごと火にかける。沸騰したら茹で汁を捨て、水で洗ってアクを流す。
- 小豆を煮る
- 圧力鍋に小豆、水適量を入れて落しぶたをしてふたをし、圧力を高圧(80kPa)にセットして中火にかける。
- 圧力がかかったら弱火にして10分煮て火を止める。
- 圧力が下がったらふたを開け、小豆をざるにあけて水気を切る。
- あんこを練る
- 鍋に小豆、きび砂糖、水少量を入れて火にかける。
- 焦げないようにへらで混ぜながら水分を飛ばし、へらですくって落とすと角が立つ硬さになったら火を止める。
- 冷ます
- ヘラですくってバットなど平たい器に取りだし、冷ます。




結果

出来上がったあんこがこちら。左が「A.渋切りあり」、右が「B.渋切りなし」です。
出来上がりの量は「あり」が約570g、「なし」が約560gだったので練り加減はほぼ同じです。
まずは見た目、硬さ、粘りなど、味以外の要素を比べてみます。
味以外の感想
見た目
写真では分かりづらいかもしれませんが、「なし」の方が濃くて暗い色をしています。
質感(熱いうち)
ヘラで混ぜながら水分を飛ばす際、手に伝わる感覚が全く違いました。
「なし」の方が粘りが強く、ややべたっとしていました。へらから離れづらいので練り加減の見極めが難しかったです。
Bの粘りが強くなったのは、渋切りの有無も影響しているとは思いますが、小豆のゆで汁を使用したのが大きな原因ではないかと思います。
小豆のゆで汁は冷蔵庫で冷やすとぷるぷるに固まります。これが粘りの増加にも繋がっているのではないでしょうか。
質感(冷めてから)
「あり」滑らかですが、「なし」はややほろほろとしています。
「なし」は「あり」よりも冷めた時に固くなりやすいの でしょうか?もう少し緩めに練り上げれば、あり同様の滑らかな食感に仕上がったのかもしれません 。
そのまま食べた感想
いよいよ実際に食べ比べを行います。
まずは何も手は加えず、あんこそのままで食べてみます。
食べる順番で印象が変わる可能性を考え、実験は3日連続で行い、AとBの食べる順番は毎日入れ替えました。
A 渋切りあり
渋切りをしていても、回数がそれほど多くないので小豆の風味は失われていません。
渋切りのせいで小豆の味が弱くなるというのは考え過ぎだったのかもしれません。
しっかり小豆の味が感じられて、大満足の小豆感。 いつも通りのおいしいあんこでした。
B 渋切りなし
がつん!と小豆の風味が感じられておいしいです。きび砂糖を使用しているのも相まってか、様々な味が感じられてAよりも味が濃い印象を受けます。
小豆そのものの味が好きな人にはおすすめな味です。
しかし、Aを食べた直後に食べると少し主張が強くクセのある味に感じられます。
悪くはないのですが、俗っぽいというか野性味があるというか。「あり」の方がより澄んだ上品な味には感じます。
きび砂糖を使ってみた感想
きび砂糖を使用しても、想像していたよりはあっさりとした味になりました。
黒蜜のような味になるのかと思っていましたが、黒糖と違いそこまではサトウキビの味は強くならないようです。
しかし、白砂糖のあんこと比べると複雑な味やコクが感じられるように思います。深みがあって、きび砂糖のあんこもとてもおいしいです。
おしるこにした感想
次に、おしるこを作って食べ比べてみました
あんこ300gを水200mlで溶き、塩0.8gを加えて温め、焼いた玄米餅を乗せました。
見た目と質感

左が「A.渋切りあり」、右が「B.渋切りなし」です。
こちらもあんこ同様、写真ではわかりにくいですが「なし」の方が色が濃く仕上がりました。
また、「なし」の方がとろみが強くてややどろりとしています。あんこ自体の粘りによる差でしょう。
味
色が濃い「なし」の方が見た目はおいしそうだったのですが、しかし味は「あり」の方がおいしく感じました。
「なし」は小豆の強い個性が雑味に感じられます。苦味やえぐみによって味が雑然とし、甘みや塩気を感じづらくなっているように思いました。
「あり」の方が味が素直と言ったらよいのでしょうか、おしるこの場合はすっきりとしている方が小豆の味を感じやすくなるのかもしれません。
おしるこにするのであれば、一般的に言われているように渋切りはした方が良さそうです。
しかしそれは、このレシピが「あり」のあんこに合わせて作られているからとも考えられます。もっと「なし」にあった味付けや作り方があるのではないかとも思いました。
まとめ あんこに渋切りは必要か
あんこに渋切りは本当に必要なのか
「必須ではないが した方が無難」
というのが現時点での結論です。
渋切りなしでも大きな失敗はしない
「なし」のあんこはたしかに味が濃いですが、食べられないほどエグくなることはありませんでした。強い風味と素朴な味わいには、「なし」ならではの魅力も感じられます。
おしるこに使う場合は「あり」の方がおいしいですが、「なし」もまずくはなかったので渋切りは絶対に必要というほどではないように思います。
渋切りありは汎用性が高い
しかし、小豆の味が苦手な人には「なし」はクセが強く感じるかもしれません。
また、まわりの生地や一緒に添えるフルーツなど、ほかの素材の味を引き立てたい場合にはしっかり渋切りをしてあんこの味をおさえた方が良さそうです。
逆に小豆の風味を強めにしたい場合でも、渋切り1~2回くらいであれば小豆の風味は強く残ります。
渋切りが裏目に出ることはあまりなさそうなので、迷った時には1~2回渋切りしておけば、何にでも使いやすい万能なあんこが出来上がるのではないでしょうか。
渋切りなしはまだまだ未開拓
今回の結果だけで完全な結論を出すのは難しく、何度もあんこを作るうちに考えが変っていくかもしれません。
なにより渋切りをしないあんこは初めて作ったので、まだまだ分からないことが多いように思いました。
そのままとおしるこ以外の使い方ではまた印象が変わるかもしれません。
それに、ありとなしの味の違いに合わせて、同じお菓子でも作り方や味付けを変えるべきなのではないかとも思います。
どんなお菓子に使うかや、表現したい味によっておいしいあんこは変わってくるのかな、と今のところは思います。
以上、渋切りありとなし、2つのあんこの食べ比べでした。



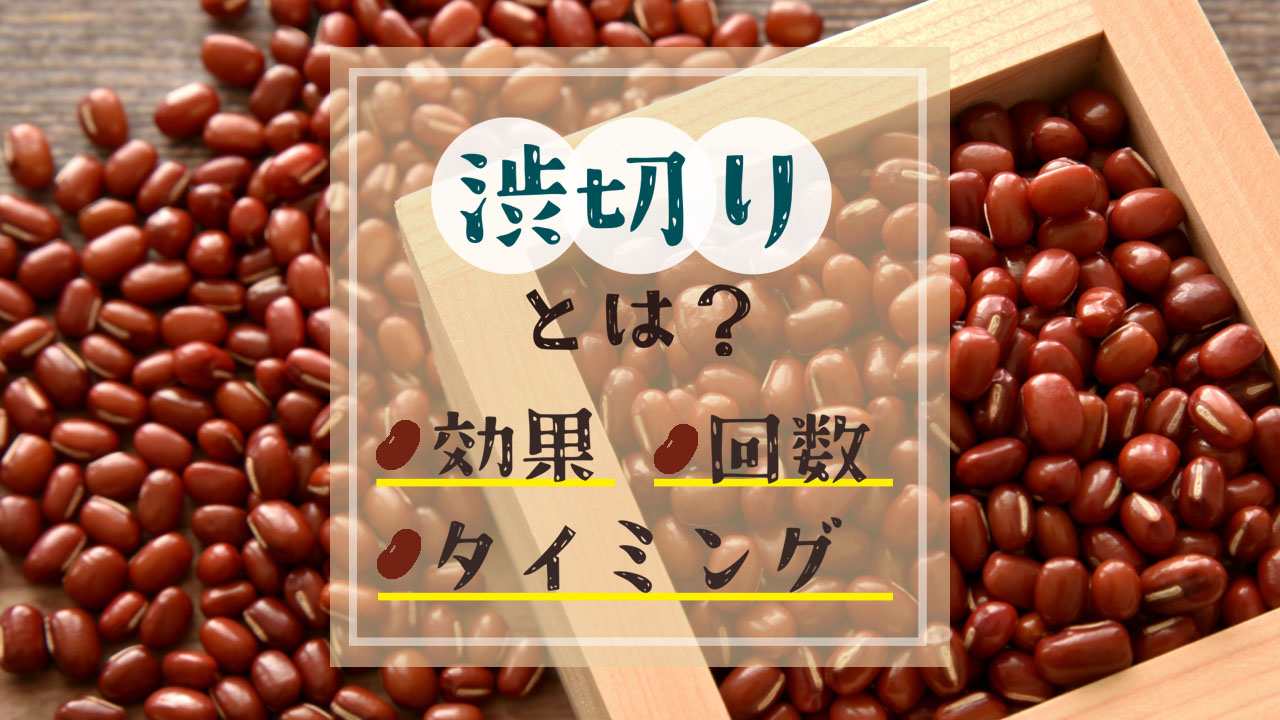 渋切りとは?効果や回数、タイミングについて
渋切りとは?効果や回数、タイミングについて